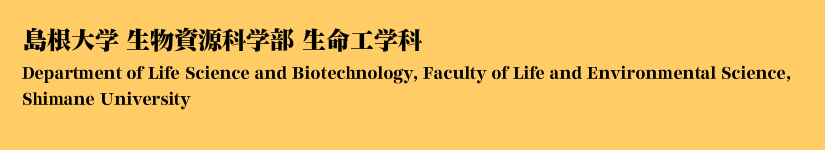島根大学 生物資源科学部 生命工学科 生命工第1研究室(分子細胞生物学研究室)
生命工第1研究室(分子細胞生物学研究室)
- 教授 横田 一成(Kazushige Yokota)
- ホルモンや代謝調節因子のような細胞外信号分子による細胞応答反応として、動物細胞のアラキドン酸カスケード反応の活性化がある。アラキドン酸カスケード反応とは、必須脂肪酸のアラキドン酸に由来し細胞内及び細胞間で働く一群の細胞情報伝達因子の生合成経路のことをいう。この生合成経路の調節機構や代謝産物の役割を細胞や分子のレベルで研究している。主に、哺乳動物培養細胞株を実験材料にして、生命科学に関する種々の実験手法を導入している。これらのカスケード反応で生合成されるエイコサノイド類は、動脈硬化、肥満、細胞増殖、細胞分化、免疫、神経機能などの多様な生命現象に関連するので、これらの周辺分野は食品機能や医薬品開発の基礎研究の宝庫となっている。
- 准教授 地阪 光生(Mitsuo Jisaka)
- 細胞内の脂質は様々な生理活性物質を生合成する原料となる。この生合成の過程には、高度に制御された過酸化反応が利用される。この過酸化反応を触媒する諸酵素を中心に、脂質から様々な生理活性物質を生合成する代謝系に関与する諸酵素の構造・反応機構・発現調節機構、および、代謝生成物の同定と生理機能の解析を通じ、本代謝系を活用した生体の巧妙な生理調節機能の解明とその活用を目的として、研究を進めている。
- 准教授 清水 英寿(Hidehisa Shimizu)
- (1)腸内細菌がヒトの健康に影響を与えている事は知られているが、どのようなメカニズムで影響を与えているのか、未だ不明な点が多い。そこで、食習慣を起因として産生量が変化する腸内細菌代謝物に焦点を当て、各種臓器に与える影響について解析を進めている。
- (2)湖沼の富栄養化に伴って異常増殖した藍藻類が産生する毒素に着目し、その毒素を含む水の直接摂取、またはそこで養殖された魚介類体内で蓄積された毒素の間接摂取で引き起こされると予想される臓器障害メカニズムについて、「食の安全性」をキーワードに解明する事を目指している。
- (3)上記(1)と(2)で得られた研究結果を基盤にして、予防・改善効果が期待される食成分を島根県になじみがある「食」から探索し、その評価・検証を行う。